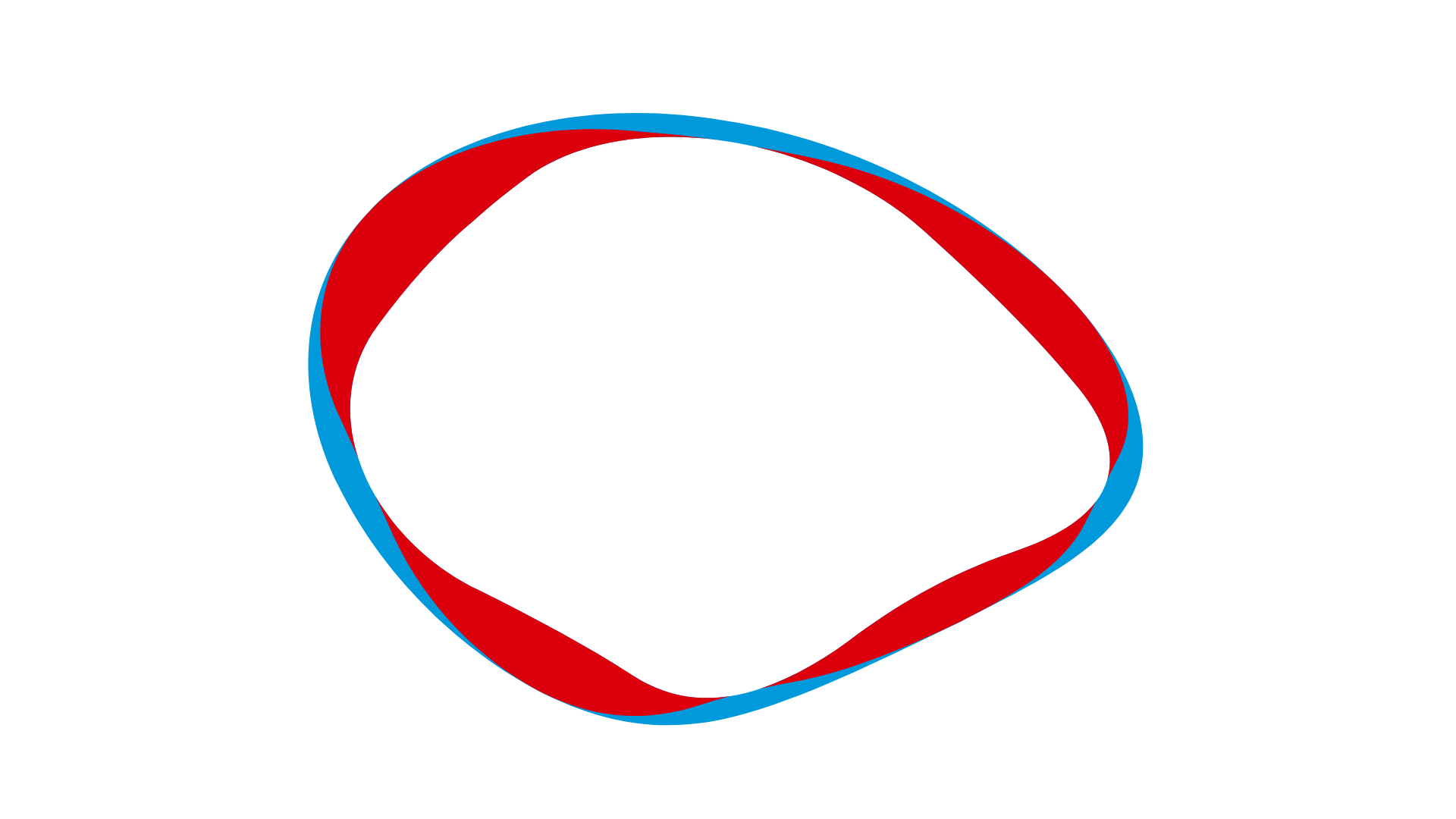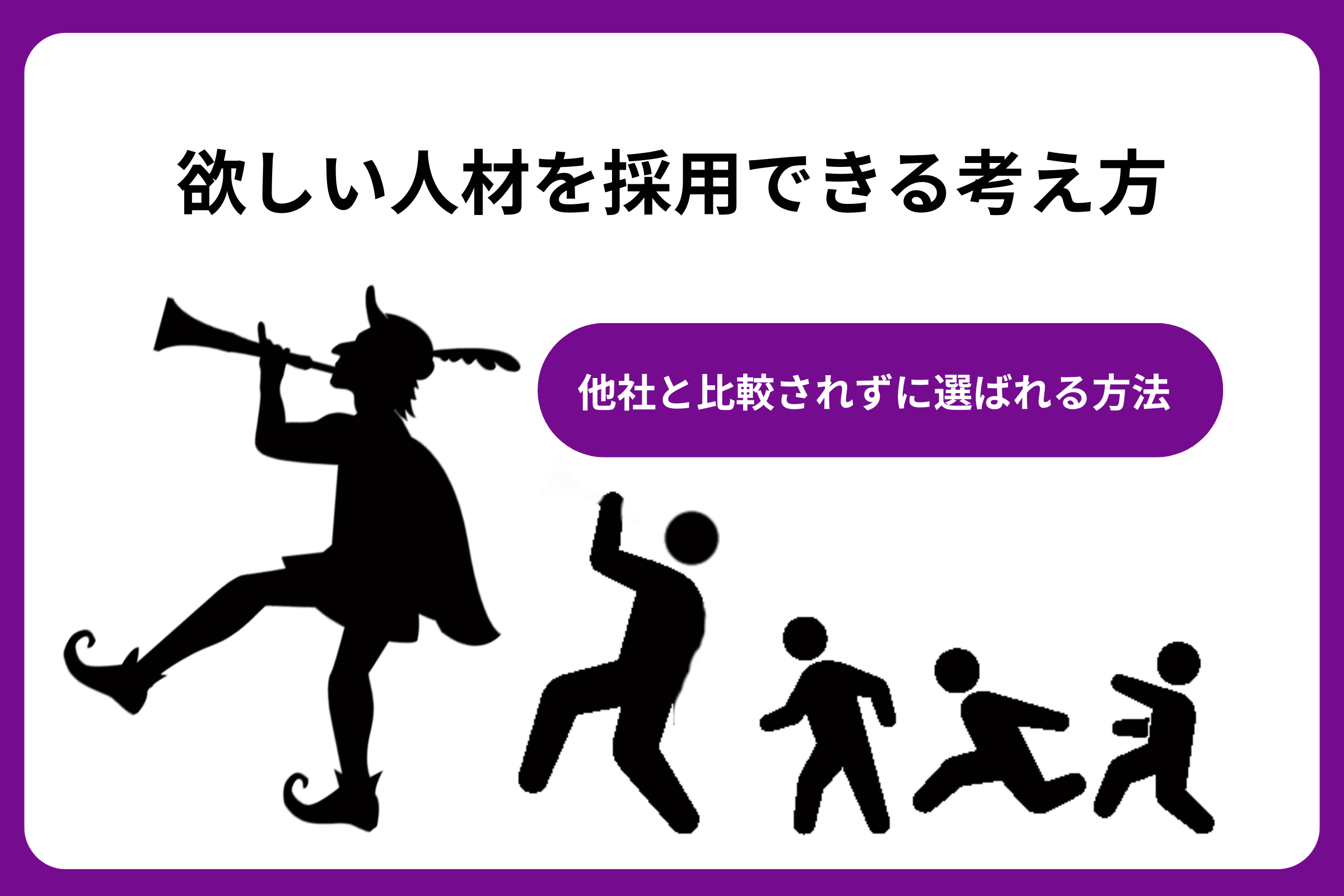
欲しい人材を採用できる考え方
はじめに:なぜ今、採用の「考え方」が重要なのか?
「なかなか良い人が採用できない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「そもそも応募が集まらない」 企業の成長にとって「人材」が不可欠であることは言うまでもありませんが、その採用活動において、このような悩みを抱える企業は少なくありません。特に近年、採用を取り巻く環境は大きく変化しており、従来通りのやり方では通用しなくなってきています。
採用市場の変化と企業が直面する課題
まず、大きな変化として挙げられるのが「労働人口の減少」です。少子高齢化が進む日本では、働き手の数が年々減少しており、企業は限られた人材を奪い合う状況、つまり「売り手市場」が常態化しています。これにより、企業は候補者から「選ばれる」立場となり、より魅力的な情報発信や採用体験の提供が求められるようになりました。
また、「働き方の多様化」や「価値観の変化」も見逃せません。終身雇用が当たり前ではなくなり、転職はキャリアアップの一般的な選択肢となりました。働く人々は、給与や待遇だけでなく、仕事のやりがい、自己成長の機会、良好な人間関係、ワークライフバランス、企業の社会貢献性など、より多くの要素を重視するようになっています。
さらに、インターネットやSNSの普及により、企業の評判や口コミは瞬時に広まるようになりました。いわゆる「ブラック企業」のレッテルを貼られれば、採用活動に大きなダメージを受けることは避けられません。
「とりあえず採用」から「戦略的採用」へ
このような厳しい採用環境の中で、企業が求める人材を獲得し、定着・活躍してもらうためには、単に求人広告を出して応募を待つような「とりあえず採用」では立ち行かなくなっています。
必要なのは、自社の経営目標や事業計画と連動させ、「どのような人材を」「いつまでに」「何人」「どのようにして」採用するのかを明確に定め、計画的に実行していく「戦略的採用」の考え方です。
この記事では、なぜ採用戦略が必要なのか、そして、欲しい人材を獲得するために具体的にどのようなステップで考え、行動していくべきなのかを、分かりやすく解説していきます。特に、採用リソースが限られがちな中小企業の経営者や人事担当者の方々にとって、自社の採用活動を見直し、成功へと導くためのヒントを提供できれば幸いです。
採用戦略とは何か?なぜ必要なのか?
「採用戦略」と聞くと、何か難しいことのように感じるかもしれません。しかし、決して特別なことではありません。簡単に言えば、「場当たり的ではない、計画的な採用活動の進め方」のことです。
採用戦略の定義:場当たり的ではない計画的な採用活動
具体的には、以下の要素を明確にし、一貫性を持って実行していくことが採用戦略の骨子となります。
- 採用目標の設定: 企業の経営目標や事業計画に基づき、「いつまでに」「どのようなポジションに」「何人」の人材が必要かを明確にします。
- 求める人物像(ペルソナ)の定義: 必要なスキルや経験だけでなく、自社の文化や価値観にマッチする人物像を具体的に描きます。
- 自社の魅力の明確化と発信: ターゲットとなる人材にとって魅力的に映る自社の強み(事業内容、社風、待遇、成長機会など)を整理し、効果的に伝えます。
- 採用チャネルの選定: ターゲット人材に最も効果的にアプローチできる採用手法(求人媒体、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など)を選択します。
- 選考プロセスの設計: 求める人物像を適切に見極め、かつ候補者の入社意欲を高めるような選考フローを構築します。
- 効果測定と改善: 採用活動の成果をデータで把握し、継続的に改善していく仕組みを作ります。
これらの要素を事前にしっかりと計画しておくことで、勘や経験だけに頼らない、再現性のある採用活動が可能になります。
採用戦略がないことによるリスク
逆に、採用戦略がないまま場当たり的に採用活動を進めると、以下のようなリスクが生じやすくなります。
- ミスマッチの発生: 求める人物像が曖昧なため、スキルや価値観が自社に合わない人材を採用してしまい、早期離職につながる。
- 採用コストの増大: ターゲットが不明確なまま手当たり次第に求人を出したり、効果の薄い採用手法に費用をかけ続けたりすることで、無駄なコストが発生する。
- 採用工数の増加: 選考基準が曖昧なため、面接に時間がかかったり、関係者間での評価がぶれたりして、人事担当者や現場の負担が増える。
- 採用機会の損失: 自社の魅力が候補者に伝わらず、本来なら採用できたはずの優秀な人材を取り逃がす。
- 経営目標達成への遅延: 事業計画に必要な人材を計画通りに確保できず、事業の成長スピードが鈍化する。
これらのリスクを回避し、採用活動を成功に導くためには、しっかりとした採用戦略を立てることが不可欠なのです。
予算: 採用活動にかけられる予算はいくらか?
これらの点を具体的に定義することで、その後のペルソナ設定や採用手法の選定などが、より的確に行えるようになります。採用目標は、採用活動全体の羅針盤となる重要な要素なのです。
中小企業こそ採用戦略をしっかりと考える必要がある
「採用戦略なんて、大手企業がやることで、うちのような中小企業には関係ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、実際はその逆です。中小企業こそ、採用戦略をしっかりと考える必要があります。
大手企業との採用競争における中小企業の立ち位置
採用市場において、中小企業は大手企業と比較して、一般的に以下のような点で不利な状況に置かれがちです。
- 知名度・ブランド力: 大手企業ほどの知名度がないため、そもそも候補者の認知を得にくい。
- 採用予算: 採用活動にかけられる予算が限られていることが多い。
- 採用体制: 専任の人事担当者がいなかったり、少人数で他の業務と兼務していたりすることが多い。
- 待遇面: 大手企業と同水準の給与や福利厚生を提供することが難しい場合がある。
このような状況下で、大手企業と同じ土俵で、同じようなやり方で採用活動を行っても、優秀な人材を獲得することは非常に困難です。だからこそ、中小企業は自社の置かれた状況を理解し、大手企業にはない独自の強みや魅力を活かした、戦略的な採用活動を展開する必要があるのです。
採用戦略が中小企業にもたらすメリット
中小企業が採用戦略をしっかりと立てることで、以下のようなメリットが期待できます。
- 採用の成功率向上: ターゲットを明確にし、自社の魅力に合った人材に的を絞ってアプローチすることで、ミスマッチを防ぎ、採用の成功率を高めることができます。
- 採用コストの最適化: 限られた予算の中で、最も効果的な採用チャネルや手法を選択することで、無駄なコストを削減し、費用対効果の高い採用活動が実現できます。
- 自社の魅力の再発見と向上: 採用戦略を立てる過程で、自社の強みや課題を客観的に見つめ直す機会が得られます。これにより、社内制度の改善や、より魅力的な職場環境づくりにつながることもあります。
- 社員のエンゲージメント向上: 採用活動に現場の社員を巻き込むことで、自社の魅力について改めて考えるきっかけとなり、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)向上にもつながります。
- 企業の成長加速: 自社の成長に必要な人材を計画的に獲得することで、事業目標の達成を後押しし、企業の持続的な成長を実現できます。
限られたリソースを最大限に活かすために
中小企業にとって、ヒト・モノ・カネといったリソースは限られています。採用活動においても同様です。だからこそ、「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかを徹底的に考え抜き、選択と集中を行うことが重要になります。
採用戦略は、そのための道筋を示してくれるものです。漠然と活動するのではなく、明確な意図を持って採用活動に取り組むことで、限られたリソースを最大限に活かし、大手企業にも負けない採用力を身につけることができるのです。
欲しい人材を採用するための具体的なステップ
では、実際に欲しい人材を採用するためには、どのようなステップで進めていけば良いのでしょうか?ここでは、採用戦略を具体的な行動に落とし込むための6つのステップを解説します。
ステップ1:採用ターゲット(ペルソナ)を明確にする
採用活動の出発点は、「どのような人材に来てほしいのか」を具体的に定義することです。これを「採用ペルソナ」の設定と呼びます。
- どのような人材が自社に必要か? 単に「優秀な人」「即戦力」といった曖昧な言葉ではなく、担当する業務内容や役割、チーム構成などを考慮し、必要なスキル、経験、知識、資格などを具体的に洗い出します。例えば、「Webマーケティング担当者」を採用する場合、「SEOの実務経験3年以上」「Google Analyticsを用いた分析スキル」「コンテンツマーケティングの企画・実行経験」といった具体的な要件を設定します。
- 経験・スキルだけでなく価値観のマッチングも考慮する スキルや経験がいくら高くても、自社の企業文化や価値観に合わなければ、早期離職につながる可能性があります。そのため、ペルソナ設定においては、以下のような要素も考慮することが重要です。
- 価値観・志向: どのような働き方を好み、仕事に何を求めているか?(例:チームワーク重視、チャレンジ精神旺盛、安定志向)
- 性格・パーソナリティ: どのような性格特性が自社の風土に合うか?(例:協調性がある、主体性がある、粘り強い)
- キャリアプラン: 将来的にどのようなキャリアを築きたいと考えているか?
ペルソナを詳細に設定することで、その後の採用広報や選考プロセスにおいて、「誰に」「何を」伝えるべきかが明確になり、ミスマッチのリスクを大幅に減らすことができます。
ステップ2:自社の魅力を言語化する
ターゲットとなるペルソナが明確になったら、次はそのペルソナにとって魅力的に映る「自社の強み」を整理し、分かりやすい言葉で表現(言語化)する必要があります。候補者は数ある企業の中から、自分に合った会社を選ぼうとしています。自社の魅力を効果的に伝えられなければ、競争に勝つことはできません。
- 採用成功するために明確にすべき6つの企業の魅力 企業の魅力を整理する際には、以下の6つの観点から考えてみると良いでしょう。これは、求職者が企業を選ぶ際に重視するポイントを網羅的に捉えるためのフレームワークです。
- 事業・仕事の魅力 (Vision/Mission/Value):
- どのような事業を行っているか?その社会的意義は何か? (例:環境問題の解決に貢献する、地域社会を活性化させる)
- 仕事内容のやりがいや面白みは何か? (例:最先端技術に携われる、顧客から直接感謝される、大きな裁量を持って働ける)
- 会社のビジョンやミッションに共感できるか? (例:業界No.1を目指す、新しい価値を創造する)
- この会社で働くことで、どのような自己実現が可能か?
- 組織風土・文化の魅力 (Culture):
- どのような社風か? (例:風通しが良い、アットホーム、実力主義、チームワーク重視)
- どのような価値観が大切にされているか? (例:挑戦、誠実、顧客第一)
- 社員同士のコミュニケーションは活発か? (例:部署間の交流イベントがある、役職に関係なく意見を言いやすい)
- 多様な働き方への理解はあるか? (例:リモートワーク、時短勤務)
- 共に働く人の魅力 (People):
- どのような人が働いているか? (例:経験豊富なベテランが多い、若手が多く活気がある、多様なバックグラウンドを持つ人がいる)
- 経営者や上司はどのような人か? (例:ビジョンが明確、部下の成長を支援してくれる、現場の意見を聞いてくれる)
- 魅力的なロールモデルとなる社員はいるか?
- チームの雰囲気はどうか?
- 待遇・福利厚生の魅力 (Compensation/Benefit):
- 給与水準は適切か?評価制度は明確か? (例:成果に応じたインセンティブ、透明性の高い評価制度)
- 福利厚生は充実しているか? (例:住宅手当、家族手当、退職金制度、独自の休暇制度、社員食堂、資格取得支援)
- ワークライフバランスは保てるか? (例:残業時間の実態、有給休暇の取得しやすさ)
- スキルアップ・キャリア開発の魅力 (Development):
- どのようなスキルや経験が身につくか? (例:専門性の高いスキル、マネジメント経験、新規事業立ち上げ経験)
- 研修制度や教育制度は充実しているか? (例:OJT、外部研修参加支援、資格取得支援)
- キャリアパスは明確か? (例:ジョブローテーション制度、社内公募制度、昇進・昇格の基準)
- 成長できる環境があるか? (例:挑戦を推奨する文化、フィードバックが得られる機会)
- 会社の安定性・将来性の魅力 (Stability/Future):
- 会社の経営状況は安定しているか? (例:業績推移、自己資本比率)
- 事業の将来性や成長性はどうか? (例:市場の成長性、競合優位性、新規事業への取り組み)
- 業界内でのポジションは?
- 変化に対応できる柔軟性はあるか?
- 事業・仕事の魅力 (Vision/Mission/Value):
- ターゲットに響く魅力の見せ方 洗い出した魅力を、設定したペルソナに合わせてカスタマイズして伝えることも重要です。例えば、若手の成長意欲が高いペルソナには「スキルアップ・キャリア開発の魅力」を、安定志向のペルソナには「会社の安定性・将来性の魅力」や「待遇・福利厚生の魅力」を強調するなど、相手のニーズに合わせて訴求ポイントを変える工夫が必要です。
ステップ3:適切な採用チャネルを選定する
自社の魅力が言語化できたら、次はその魅力をターゲット人材に届けるための「採用チャネル(経路)」を選定します。代表的な採用チャネルには以下のようなものがあります。
- 求人媒体: リクナビNEXT、マイナビ転職などの総合型サイト、特定の職種や業界に特化した専門サイト、Indeedなどの求人検索エンジンなど。幅広い層にアプローチできますが、競合も多く、埋もれてしまう可能性もあります。
- 人材紹介(エージェント): 企業と求職者の間に立ち、マッチングを行ってくれるサービス。成功報酬型が多く、採用工数を削減できますが、紹介手数料が発生します。特定のスキルを持つ人材やハイクラス層の採用に強い傾向があります。
- ダイレクトリクルーティング(スカウト): 企業がデータベースなどから直接候補者を探し、アプローチする手法。欲しい人材にピンポイントでアプローチできますが、候補者検索やスカウト文面作成などの工数がかかります。
- リファラル採用(社員紹介): 社員の人脈を通じて候補者を紹介してもらう手法。自社への理解度が高い人材を採用しやすく、採用コストも抑えられますが、紹介が出るかどうかは社員の協力次第です。
- 自社採用サイト・SNS: 自社のウェブサイトやSNSアカウントを活用して情報発信し、応募を募る手法。自社の魅力を自由に表現できますが、集客のためには工夫が必要です。
- ハローワーク: 無料で求人を掲載できる公共の職業紹介機関。地域密着型の採用に強いですが、若年層や専門職の採用には限界がある場合もあります。
- ターゲット層に合わせたチャネル選び 重要なのは、設定したペルソナが普段どのような情報収集を行い、どのようなチャネルを利用しているかを考え、それに合わせてチャネルを選択することです。例えば、若手エンジニアを採用したいなら、技術系イベントへの出展やエンジニア向け求人サイト、技術ブログでの発信などが有効かもしれません。複数のチャネルを組み合わせることも効果的です。限られた予算と工数の中で、最も費用対効果が高いチャネルを見極めましょう。
ステップ4:魅力的な求人情報を作成する
選定したチャネルで実際に候補者にアプローチするための「求人情報」を作成します。求人票、スカウトメール、採用サイトのコンテンツなどがこれにあたります。
- ターゲットの心に響くメッセージとは? 求人情報は、単なる募集要項の羅列であってはなりません。ステップ1で設定したペルソナが、思わず「この会社で働いてみたい!」と感じるような、魅力的なメッセージを込めることが重要です。
- ペルソナへの呼びかけ: 「〇〇の経験を活かしたいあなたへ」「〇〇な働き方を実現したい方へ」など、ターゲットに直接語りかけるような表現を使う。
- 共感を呼ぶストーリー: 企業のミッションやビジョン、事業の社会的意義などを伝え、候補者の価値観に訴えかける。
- 具体的なメリットの提示: その会社で働くことで得られる具体的なメリット(スキルアップ、キャリア、やりがい、働きやすさなど)を提示する。
- 候補者の疑問や不安への先回り: 候補者が抱きそうな疑問(残業時間、社風、入社後のギャップなど)に対して、正直かつ具体的に回答する姿勢を示す。
- 具体的な業務内容や働く環境を伝える工夫 仕事内容や働く環境については、できるだけ具体的に、イメージしやすいように記述します。
- 業務内容: 単に「〇〇業務」と書くのではなく、「〇〇ツールを使って△△の分析を行い、□□の改善提案を行う」のように、具体的なアクションや使用ツールを明記する。一日の仕事の流れや、関わるプロジェクトの事例などを紹介するのも効果的です。
- 働く環境: 職場の雰囲気、チーム構成、上司や同僚の人柄、オフィス環境(写真や動画を活用するのも有効)、リモートワークの状況などを具体的に伝える。社員インタビューなどを掲載し、実際に働く人の声を紹介するのも良いでしょう。
求人情報は、候補者が最初に企業に触れる重要な接点です。ここで魅力を感じてもらえなければ、応募にはつながりません。ステップ2で言語化した自社の魅力を最大限に活かし、ターゲットの心に響く求人情報を作成しましょう。
ステップ5:効果的な選考プロセスを設計する
応募が集まったら、次はいよいよ選考プロセスです。選考は、企業が候補者を見極める場であると同時に、候補者が企業を見極める場でもあります。効果的な選考プロセスを設計することが、採用の成功率を高める鍵となります。
- 見極めたい要素と評価基準の明確化 まず、ステップ1で設定したペルソナに基づき、「選考を通じて何を見極めたいのか」を明確にします。スキルや経験はもちろん、価値観、ポテンシャル、自社への適性など、評価すべき項目を洗い出します。 そして、各項目について具体的な評価基準を設定します。例えば、「主体性」を見極めたい場合、「過去の経験で、指示待ちではなく自ら課題を見つけて行動した具体例を話せるか」「面接での質問に対して、自分の言葉で考えを述べられるか」といった基準を設定します。 評価基準を明確にし、面接官の間で共有しておくことで、評価のブレを防ぎ、客観的で公平な選考が可能になります。構造化面接(あらかじめ質問項目や評価基準を決めておく面接手法)を取り入れるのも有効です。
- 候補者の体験(候補者エクスペリエンス)を意識する 選考プロセス全体を通じて、候補者が「この会社に入りたい」と思えるような、ポジティブな体験を提供すること(候補者エクスペリエンス、Candidate Experience = CX)が非常に重要です。
- 迅速かつ丁寧なコミュニケーション: 応募後の連絡、面接日程の調整、合否連絡などを迅速かつ丁寧に行う。連絡が遅い、対応が雑だと、候補者の志望度は下がってしまいます。
- 魅力的な面接体験: 面接官は企業の顔です。高圧的な態度や一方的な質問は避け、候補者の話を真摯に聞き、対話を通じて相互理解を深める場にする。自社の魅力も積極的に伝える。
- 分かりやすい選考プロセス: 選考フローや所要時間、評価ポイントなどを事前に候補者に伝えることで、安心して選考に臨んでもらう。
- フィードバックの提供: 可能であれば、不採用となった候補者にも、簡単な理由やフィードバックを伝えることで、企業の印象を良くすることができる場合がある。
選考プロセスは、候補者が企業を判断する重要な機会です。良い候補者体験を提供することで、優秀な人材の獲得につながるだけでなく、企業の評判向上にも貢献します。
ステップ6:内定承諾率を高めるためのフォロー
選考を経て「この人を採用したい!」という人材が見つかったら、内定を出します。しかし、安心するのはまだ早いです。特に売り手市場においては、候補者は複数の企業から内定を得ているケースも少なくありません。内定を出してから実際に入社してもらうまでの「内定承諾率」を高めるためのフォローが重要になります。
- 内定出しから入社までのコミュニケーション 内定通知は、電話やメールだけでなく、可能な限り直接会って(あるいはオンラインで顔を見て)伝えるのが望ましいでしょう。その際には、改めて採用したい理由や期待を具体的に伝え、候補者の入社意欲を高めます。 内定承諾期間中も、放置せずに定期的にコミュニケーションを取ることが大切です。例えば、
- 現場社員との面談機会の設定
- 社内イベントへの招待
- 会社やチームに関する情報提供
- 入社手続きに関する丁寧な案内 など、候補者の不安を取り除き、入社への期待感を高めるような働きかけを行います。
- オファー面談の重要性 内定通知後、条件提示や入社意思確認のために行う面談を「オファー面談」と呼びます。これは単なる条件伝達の場ではなく、候補者の疑問や不安を解消し、最終的な意思決定を後押しするための重要なコミュニケーションの機会です。 オファー面談では、給与や待遇などの条件面だけでなく、入社後の具体的な業務内容、キャリアパス、期待する役割などを改めて丁寧に説明します。また、候補者が疑問に思っていること、懸念していることを率直に聞き出し、誠実に対応することが重要です。場合によっては、条件面での交渉が必要になることもあります。
内定はゴールではなく、候補者との新しい関係のスタートです。入社までの期間、丁寧なコミュニケーションとフォローを継続することで、内定辞退を防ぎ、スムーズな入社へとつなげることができます。
採用活動の効果測定と改善
採用戦略を立てて実行したら、それで終わりではありません。その活動が実際に効果を上げているのかを測定し、改善を続けていくことが、継続的な採用成功のためには不可欠です。
採用KPIの設定とモニタリング
採用活動の成果を客観的に評価するために、重要業績評価指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定し、定期的に測定(モニタリング)します。設定すべきKPIの例としては、以下のようなものがあります。
- 応募数: 各採用チャネルからの応募者数
- 書類選考通過率: 応募者のうち、書類選考を通過した割合
- 面接通過率: 各面接段階を通過した割合
- 内定承諾率: 内定を出した候補者のうち、承諾した割合
- 採用単価: 採用者1人あたりにかかったコスト(求人広告費、人材紹介手数料、採用担当者の人件費など)
- 採用充足率: 採用目標人数に対して、実際に採用できた人数の割合
- 入社後定着率: 採用した人材が一定期間(例:1年後)定着している割合
これらのKPIを設定し、目標値と比較したり、過去のデータと比較したりすることで、採用活動のどこに課題があるのかが見えてきます。例えば、「応募数は多いが書類選考通過率が低い」のであれば、ターゲットに合わない層からの応募が多い可能性があり、求人情報の見直しや採用チャネルの変更が必要かもしれません。「内定承諾率が低い」のであれば、選考プロセスや内定後のフォローに問題がある可能性があります。
データに基づいた改善サイクルの確立
KPIのモニタリングによって課題が見えてきたら、その原因を分析し、改善策を考え、実行します。そして、改善策の効果を再びKPIで測定する、というPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回していくことが重要です。
- Plan(計画): 採用目標とKPIを設定し、具体的な採用計画を立てる。
- Do(実行): 計画に基づいて採用活動を実行する。
- Check(評価): KPIを測定し、計画通りに進んでいるか、効果が出ているかを確認し、課題を特定する。
- Action(改善): 特定された課題の原因を分析し、改善策を立案・実行する。
このサイクルを継続的に回すことで、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な判断で採用活動を改善していくことができます。
継続的な採用力強化のために
採用市場や社会情勢は常に変化しています。一度成功した方法が、今後もずっと通用するとは限りません。効果測定と改善を継続的に行い、常に最新の情報を取り入れながら採用戦略や手法をアップデートしていくことが、企業の持続的な成長を支える「採用力」の強化につながるのです。
まとめ:戦略的な採用活動で、企業の未来を創る人材を獲得しよう
ここまで、「欲しい人材を採用できる考え方」として、採用戦略の重要性から具体的なステップ、そして効果測定と改善の必要性までを解説してきました。
採用は経営課題であるという認識
採用活動は、単に人手不足を解消するための作業ではありません。企業のビジョンを実現し、事業を成長させ、未来を創っていくための、極めて重要な「経営課題」です。どのような人材を採用するかによって、企業の組織文化、競争力、そして将来そのものが大きく左右されます。
特に、変化が激しく、先行き不透明な現代においては、変化に対応し、新しい価値を生み出すことができる人材の獲得が、企業の持続的な成長のために不可欠となっています。
「考え方」を変え、行動を変えることの重要性
「良い人がいれば採用したい」という受け身の姿勢や、「これまでこうやってきたから」という前例踏襲の考え方では、厳しい採用競争を勝ち抜くことはできません。
まず、採用に対する「考え方」を、場当たり的なものから戦略的なものへと転換することが重要です。そして、その考え方に基づいて、具体的な「行動」を変えていく必要があります。
- 自社の未来を見据え、本当に必要な人材像を明確にする。
- 自社の持つ本当の魅力を客観的に分析し、自信を持って伝える。
- ターゲットに響くメッセージを考え抜き、最適な方法で届ける。
- 候補者一人ひとりに真摯に向き合い、最高の採用体験を提供する。
- 活動の結果をデータで検証し、常に改善を続ける。
これらの行動は、決して簡単なことではありません。時間も労力もかかります。しかし、この地道な取り組みこそが、欲しい人材を採用し、企業の成長を加速させるための最も確実な道筋なのです。
継続的な取り組みが成功の鍵
採用戦略の構築と実践は、一度行えば終わりというものではありません。企業の状況や市場環境の変化に合わせて、常に見直し、改善していく必要があります。
この記事で紹介した考え方やステップを参考に、ぜひ自社の採用活動を見つめ直し、戦略的な採用への第一歩を踏み出してください。貴社が未来を共に創る素晴らしい人材と出会い、更なる発展を遂げられることを心より願っております。
もし、採用戦略の策定や実行において、「何から手をつければ良いか分からない」「自社だけでは難しい」と感じている場合は、外部の支援サービスを活用することも有効な選択肢の一つです。採用のプロフェッショナルが、貴社の状況に合わせた最適な採用戦略の立案から実行までをサポートし、採用成功への道のりを共に歩みます。
知名度が低くても有望な人材が集まる秘訣教えます!
採用ブランディング支援サービス